私たち(ウイスキー文化研究所)が毎年発行している『日本蒸留所年鑑』、ジャパニーズウイスキーイヤーブックの最新版(2025年版)に掲載されている蒸留所の数は、ついに90を超えることになった。
2年前に出版した2023年版が、60前後だったことを考えると、わずか2年で35 ヵ所近く増えたことになる。これは現在稼働中の蒸留所の数で、これに計画中のものも入れると、その数は120を超えることになる。
もちろん、この中にはサントリーやニッカ(アサヒビール)、キリンビールなどの大手酒造メーカーの蒸留所6ヵ所も含まれていて、それ以外の80超がクラフトウイスキー、クラフトウイスキー蒸留所ということになるのだ。
クラフトウイスキー、クラフト蒸留所という言い方が流布しはじめたのは2010年頃からで、それ以前はマイクロ蒸留所という言い方のほうが一般的だった。日本だけでなく、アメリカやカナダ、そしてウイスキーの本場であるスコットランド(英国)やアイルランドで、小さな蒸留所が相次いで建てられるようになったのは、おもに2010年以降のことである。特に2015年からの10年間で、多くの小さな蒸留所がオープンし、クラフトウイスキー、クラフト蒸留所という言い方が一般的になってきた。

同スペイサイドにあるザ・グレンリベット蒸留所。スチルは合計28基。グレンフィディックとシングルモルトNo.1の座を争っている
従来の大手蒸留所とクラフト蒸留所を分ける明確な定義はないが、一度の仕込み(これをワンバッチという)で使う麦芽量、穀物量が1~2トンのものまでを、便宜的にクラフト蒸留所と括るのが、現在は一般的となりつつある。大手でもクラフト的な造りをしているところはあるし、小さくてもコンピューター管理の全自動というところもある。造りのスタイルで分けるのが難しいことから、一度の仕込みサイズで分けようというのがそのコンセプトだ。
例えばモルトウイスキーでいうと原料はすべて大麦の麦芽(これをモルトという)で、この大麦麦芽1 ~ 2トンを使って仕込んでいるのが、いわば標準サイズ。
中でも1トンというのが、クラフト蒸留所では、最も多い仕込みサイズである。
モルトウイスキーは麦芽を粉砕し、仕込水(温水)に混ぜて、マッシュタンと呼ばれる糖化槽でデンプンを糖化し、それをウォッシュバックという発酵槽に移して発酵させる。
もちろん糖化は麦芽中に生成されるデンプン糖化酵素の働きで行われ、発酵はイースト菌によって行われる。ビールとここまではほぼ同じ工程で、3 ~ 4日の発酵でアルコール分7~9%くらいのモロミができあがる。
次にこれをポットスチルという銅製の単式蒸留器に移して蒸留が行われるが、モルトウイスキーの場合は、初留と再留という2回の蒸留を行い、アルコール分70%ほどのニューポットと呼ばれるスピリッツを得ている。
これを63%前後まで加水して木製樽に詰めて熟成させるというのが、モルトウイスキーのおおまかなプロセスである。
麦芽1トンあたりから得られるアルコールの量は100%アルコール換算で約400リットル。これを63%前後に加水するということは、一度の仕込みで200リットルのバーボンバレル樽(容量200リットル)にして、約3樽できるということになる。クラフト蒸留所では、一日に一仕込みというところがほとんどなので、週5日稼働してもせいぜい15樽。年間50週稼働して、やっと700~750樽くらいを造ることができる。
サントリーやニッカ、キリンなどの大手メーカーの生産データが出ていないので分からないが、例えばスコッチのモルトウイスキー蒸留所で最大のところはグレンリベットとグレンフィディックの2つで、ここの生産能力は共に年間2,100万リットルにものぼる。多くのクラフト蒸留所が10万リットル前後であるのと比べると、200倍ほどの規模ということになる。つまり蒸留所が 詰める樽はそれぞれ年間約18万樽にもなるのだ。
いかにクラフトと大手蒸留所との間に大きな差があるか、分かるというものだ。
ウイスキーの出荷量は1980 年代前半をピークに25 年間低迷
日本は1980年代前半をピークに長い間ウイスキー不況に悩んできた。1983年のウイスキーの出荷量(国内製造、外国産含めて)は年間で約38万キロリットル。
数字が大きすぎてよく分からないが、これを700ミリリットルボトル換算にすると約5億4,300万本となる。つまり当時は国民一人当たり、年間で約5.5本のウイスキーを飲んでいたことになる。
それがバブル期を過ぎても消費低迷が一向に改善されず、なんと2007 ~ 2008年まで、右肩下がりが続いたのだ。2008年の出荷量は約6万5,000キロリットルで、ピーク時の6分の1。
ボトル本数にして約9,300万本にまで落ち込んでしまった。そのダウントレンドから25年ぶりにアップトレンドに向かったのが2008年で、この頃角ハイボールなどのハイボール訴求が広がり、再びウイスキーの出荷量が上昇に向かった。現在はかつてほどではないが、16~18万キロリットルまで回復している。それでもまだピーク時の半分以下でしかない。実は日本のクラフトウイスキーブーム、クラフト蒸留所ムーブメントは、まさにこの、どん底時代に始
まっているといっても過言ではない。それを象徴するのが2008年2月に蒸留開始となったベンチャーウイスキーの秩父蒸溜所である。
埼玉県秩父市に秩父蒸溜所が創業するまで(創業は前年の2007年)、日本には大手3社、サントリーの山崎蒸溜所、白州蒸溜所、知多蒸溜所、ニッカの余市、宮城峡、そしてキリンの富士御殿場の6つの蒸留所しかなかった。
クラフトサイズの小さな江井ヶ嶋蒸留所や本坊酒造のマルス信州蒸溜所はあったが、何年も自社蒸留は途絶えていたし、大手とは比べものにならないくらいに小さかった。

埼玉県秩父市の、みどりヶ丘工業団地にあるベンチャーウイスキーの秩父蒸溜所。蒸留開始は2008年2月で、これが日本のクラフト蒸留所の先駆けとなった。

1923年に創業した我が国初の本格蒸留所が山崎蒸溜所。京都と大阪府の境にある天王山の麓に位置する。

サントリーの知多蒸溜所。1973年に生産開始となったグレーンウイスキー専用蒸留所だ。

1934年に創業したニッカウヰスキーの余市蒸溜所。世界でも唯一となった石炭直火焚蒸留を行っている。しめ縄が飾られたポットスチルもニッカだけのもの。

1973 年に創業したキリンの富士御殿場蒸溜所。シーグラム社、シーバス社、キリンの3社合弁会社としてスタートした。
大手の6蒸留所もフル生産にはほど遠く、生産能力の1 ~ 2割程度の製造を継続するのが精一杯だった。それほど、ウイスキーは飲まれていなかったのだ。
そんな大逆風の中スタートしたのが、ベンチャーウイスキーの秩父蒸溜所で、創業者は秩父で代々日本酒の蔵を営んできた肥土家の肥土伊知郎氏である。父の代に同じ埼玉県の羽生市に進出し、東亜酒造を立ち上げウイスキー造りに乗り出したが、やはり90年代のウイスキー不況で、2000年には会社そのものを手放している。これが秩父の前身となる東亜酒造の羽生蒸溜所で、実際に建てられたのは1980年代前半の“地ウイスキーブーム”の頃だった。
ゴールデンホースという2級ウイスキーを造り、「北のチェリー、西のマルス、東のゴールデンホース」として、一世を風靡。全国の地ウイスキーファンを虜にしたものだ。
ちなみに北のチェリーとは福島県郡山市の笹の川酒造が造るチェリーウイスキーで、一升瓶に詰められたウイスキーとして人気を博した。西のマルスは、鹿児島の焼酎メーカー、本坊酒造が造る同じく2級ウイスキーのマルスウイスキーで、当時本坊酒造は、長野県宮田村に信州蒸溜所を(現駒ヶ岳蒸溜所)オープンさせていた(1985年)。

2016年秋に創業した本坊酒造の津貫蒸溜所。今は使われていない連続式蒸留機の蒸留棟がシンボル。

同じく本坊酒造が1985年に創業したマルス信州(現・駒ヶ岳)蒸溜所。中央アルプスの木曽駒ヶ岳の麓に建てられている。
世界中にクラフト蒸留所が誕生フランスでもすでに100を超える蒸留所が…
ちなみに上記3社のうち笹の川酒造は同敷地内に2016年に安積蒸溜所をオープンさせ、現在はここでクラフトウイスキーの安積や山桜などのブランドをつくっている。
チェリーと違って(チェリーは今もつくっている)、こちらは正真正銘の自社蒸留のジャパニーズウイスキーである。また本坊酒造は2011年にマルス信州蒸溜所を19年ぶりに再稼働させ、現在はやはりシングルモルトのマルス駒ヶ岳や、ブレンデッドの岩井トラディショナルなどを造っている。さらにクラフトブームの先駆者として、2016年には本坊酒造発祥の地である鹿児島の南さつま市加世田に、第2の蒸留所となるマルス津貫蒸溜所をオープンさせ、シングルモルトを中心に本格的にジャパニーズウイスキーを造っている。東亜酒造の羽生蒸溜所は前述のように肥土家の手を離れたが、その肥土氏が新たに秩父蒸溜所を2008年にオープンさせた。
まさにウイスキーがどん底であった時代での船出だったが、その後ウイスキーは日本だけでなく、スコットランドやアイルランド、そしてアメリカ、カナダ、さらにインドや台湾、中国、タイ、イスラエル、さらにはヨーロッパで、爆発的な人気となり、スコットランドでもこの10年で50近い蒸留所が続々とオープンしたし、アイリッシュは以前このコラムに書いたとおり、20年で蒸留所の数が10 ~ 15倍近くにも増えている。
アメリカやカナダでも、この10年で数百の小さな蒸留所が誕生している。ワインとコニャックで有名なフランスにも、なんとシングルモルトを造る蒸留所が100ヵ所以上もあるというのだ。
そしてインドを含めたアジアで、今一番成長著しいのが、お隣の中国である。世界的にはまったく知られていないが、現在中国で稼働中のウイスキー蒸留所は10~20ヵ所近くとなり、計画段階のものも含めると、その数は40近くになると推測する人もいる。それも、みなここ4~5年の話である。次回は、日本の新興クラフト蒸留所も含め、インド、台湾、中国の蒸留所についても、興味深い蒸留所をピックアップして紹介してゆこうと思っている。
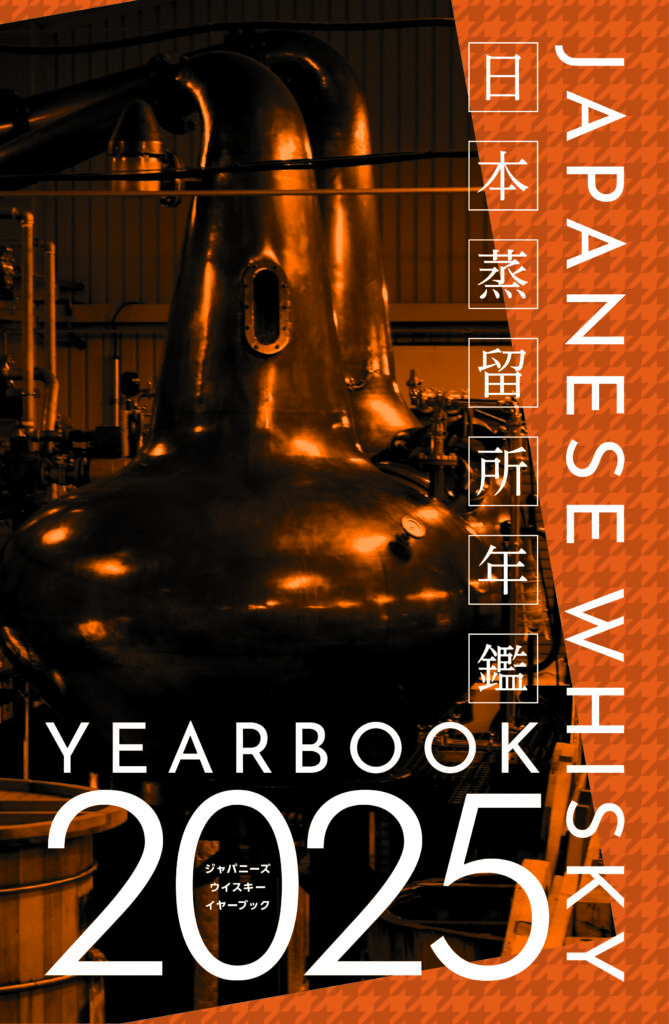
日本蒸留所年鑑 JAPANESE WHISKY YEAR BOOK 2025(ウイスキー文化研究所)


